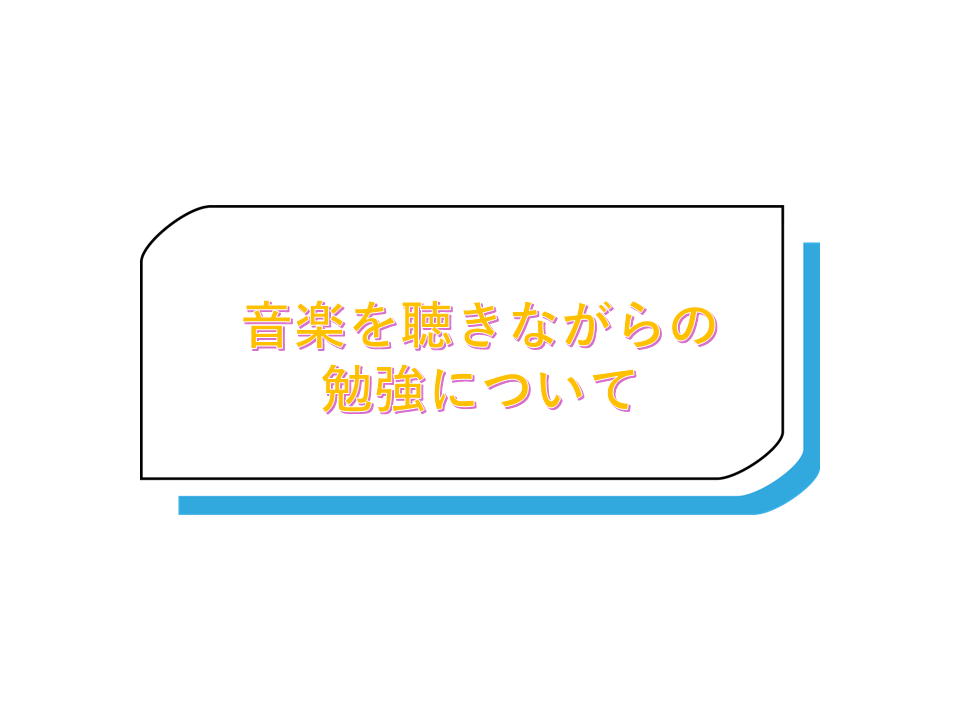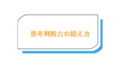生徒や保護者から「勉強中に音楽を聴いても良いか」「音楽を聴きながら勉強しているけどいみあるのかしら」というようなご相談を頂きます。
今回は音楽を聴きながら勉強することのメリットデメリットについてご紹介します。音楽を聴きながら勉強することは集中力を高めてくれるようなメリットがある反面、音楽によっては逆に気が散ってしまうデメリットもあるので、正しく使うことが大切です。
音楽が勉強に与えるメリット
1,周囲の雑音をカットできる
勉強したいけど、周りが少しうるさくて集中できないときありますよね。
家族の話し声や外の騒音をかきけして、集中しやすくなります。特にカフェやファミレスなどの周囲の音が気になる場所で効果があります。
歌詞のないBGMであったりホワイトノイズで雑音をシャットアウトするといいと思います。
2,ストレスや緊張を和らげる
ゆったりした音楽は心拍数を下げ、緊張をほぐしてくれます。定期テスト前や受験勉強など、不安を抱えているような状態での勉強に最適です。
クラシックやLo-Fiでリラックスしながら作業するのが向いていると思います。
少しおしゃれで静かなカフェとかにいくと、Lo-Fiが流れていて、集中しやすいような環境が作られていたりします。
YouTubeとかで「Lo-Fi」とか「カフェBGM」と調べるといい音源がでてきますよ。ただ、広告が入ってしまうと集中力の途切れにつながるので、広告が入らないような工夫、注意は必要になってしまいますが。
※Lo-Fiとは・・・意図的にノイズや歪み、アナログ感のある音質にすることで、温かみやチルな雰囲気を持つ音楽のジャンル
音楽が勉強に与えるデメリット
1,歌詞がある曲は集中を妨げる
人間の脳は同時に2つの言語情報を効率よく処理できません。
歌詞の言葉が脳に入ってくると、言語情報処理と競合してしまい、暗記や読解の効率を下げてしまいます。とくに国語や英語の勉強中に歌詞のある曲を聴いてしまうと、勉強の内容の処理と歌詞の処理で頭がパンクしてしまいます。
音楽を聴きながら音楽を聴く場合は、歌詞のないクラシックや作業用BGMを聴くようにしましょう。
2,複雑すぎるメロディは注意をそらす
激しい曲やテンポが変わる曲は、脳の注意が音楽に向かいやすいです。特に数学の文章題や作文など、深く考える作業では集中力が落ちやすいです。
テンポのゆっくりな曲を聴くことをお勧めします。テンポが60~70BPMの曲が集中力を持続させやすいとの研究結果もでているので、なるべくテンポの遅い曲を選びましょう。
まとめ
音楽を聴きながら勉強することのメリットとデメリットをご紹介しました。音楽の使い方、使う音楽の種類によっては、集中力を高め、効率のいい勉強ができるようになります。一方で、歌詞のある音楽など、使う音楽の種類を間違えてしまうと勉強効率が下がって逆効果になってしまいます。
当教室でも集中力を高める目的として、歌詞無しのBGMを流しています。
自宅での学習の際に、自分の好きな曲を聴いてしまうと曲に意識が向いてしまい、勉強効率が下がってしますので注意が必要です。
効率のいい勉強をしてしっかりと結果をだすためにも、音楽の正しい使い方をしましょう。